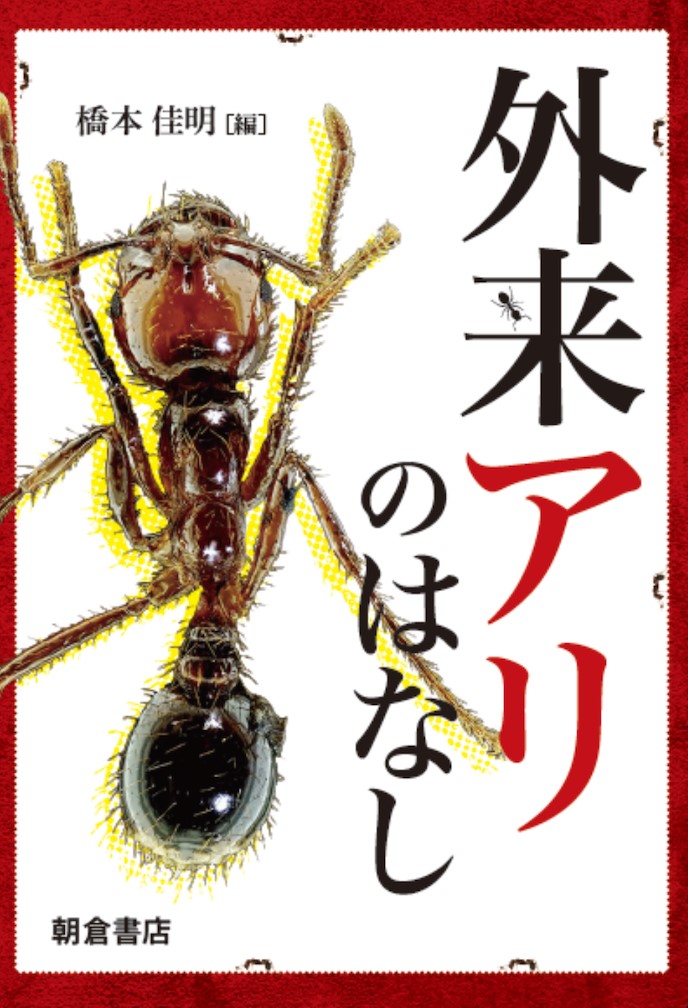ひとはくの臨時休館も5/31まで続くことになりました。
ひとはく連携活動グループ「GREEN GRASS」との共催で、
3/20(金祝)から植物画展「美しき日本の野山の植物」を行なっていますが、
3/20と21午前のみの1日半しかお見せできていません。
「GREEN GRASS」と全国の出品者のみなさんから了解がとれましたので、
やや解像度は低いですが、順次、このブロクでアップします。
45作品もありますので何回かにわけての投稿します。

3階入口付近です。まっすぐな通路の壁と右奥にあるパネルに展示しています。
最近は昼白色LEDが入手しやすくなりました。白色光の方が色がわかりやすいです。

入ってすぐ右側の展示です。ショーケースには植物標本が入っています。
以下、植物画とラベルの内容[タイトル・作者・解説)で示します。
解説は、ほどんどが黒崎史平氏(頌栄短大名誉教授)によります。
-----------------------------------
 ○タンポポ3種 Taraxacum spp.(キク科)
○タンポポ3種 Taraxacum spp.(キク科)田地川和子 TAJIKAWA, KAzuko 作
(center) カンサイタンポポ T. japonicum 神戸市北区
(right) セイヨウタンポポ T. officinale 姫路市
(left) シロバナタンポポ T. albidum 姫路市
カンサイは西日本を代表する在来種。シロバナは日本海側などに多い。このセイヨウは総苞外片の反り返りが弱く、雑種かもしれない。
兵庫県立人と自然の博物館所蔵
 ○ミツバアケビ(アケビ科)
○ミツバアケビ(アケビ科)Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.
貴島せい子 KIJIMA, Seiko 作 神戸市北区
アケビ同様に秋の味覚として親しまれている蔓植物。どちらかというとアケビより美味しい。果実が熟すと、果皮が裂開してゼリー状の胎座が現れる。この胎座を食べるが、果皮も山菜料理に使う。
 ○ハウチワカエデ(ムクロジ科)
○ハウチワカエデ(ムクロジ科)Acer japonicum Thunb.
小西恵美子 KONISHI, Mieko 作
神戸市立森林植物園
葉の形が天狗の羽団扇に似ている。日当たりによって赤や黄色に紅葉し、そのグラデーションが美しい。
 ○ソメイヨシノ(バラ科)
○ソメイヨシノ(バラ科)Cerasus x yedoensis (Matsum.) Masam. & Suzuki
肥田陽子 HIDA, Yoko 作 兵庫県芦屋市
エドヒガンとオオシマザクラの雑種由来の園芸品種。江戸末期に江戸の染井村から吉野桜として販売された。明治以降全国的に植栽され、花見と言えばソメイヨシノとなった。
ひとはく所蔵のミツバアケビとハウチワカエデの標本も展示しています。
ミツバアケビ 標本 ハウチワカデ 標本
Akebia trifoliata Acer japonicum


(鈴木武)