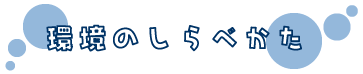| 川の環境調査といっても、色々な調査方法があります。ここではいくつかの方法を紹介します。 ■ パックテストによる水質調査 川の水を汲んで、その中にとけている物質をパックテストを使って調べる方法です。水の中に、汚れのもととなる窒素やリン酸、有機物がたくさん含まれていると、水質が悪いことになります。 川の学習では、「硝酸態窒素」、「亜硝酸」、「アンモニア」、「リン酸」、「COD」を測定することが多いようです。このなかでも、「COD」がお手軽で、経験的に最も川の水質が反映されると思いますので、お勧めします。 CODが高い場所とそこに生息する生物を比較することで、川の状態が良く分かります。 ■電気伝導度計による水質調査(ECの測定) 水の中をどれだけ電気が通りやすいかを測定するのが、電気伝導計です。汚れの成分がたくさん水の中に混じっていると、川の水が汚れていると言えます。測定は、機器があれば簡単です。 測定した値の目安は以下のとおりです。 <20μS/cm :かなりきれいな水です。源流部などが該当。 <100μS/cm :普通にきれいな川はこの程度 <200μS/cm :やや汚れた川 <200μS/cm :汚れた川 *ただし、温泉水、地質の影響や塩水などが混じる場合には、大変高い値になることがあります。 お勧めの機種は以下のものです。 コンパクト導電率計 B−173(堀場製作所) ■水生生物による水質判定 川に住んでいる水生生物の種類から、その川の水質を判定します。川の水生昆虫には、きれいな水を好む種類、汚い水でも住める種類など、いろいろな特性があります。この特性を利用するのが、「水生生物による水質判定」です。きれいな水を好む生物が多ければ、その川は「きれい」ということになります。水生昆虫の種類がわかると川の水質を判定することができます。詳しい方法は、以下のページに詳細されています。 ⇒水生生物による水質判定 (環境省) この調査の良い点は、調査した日の水質だけでなく、数ヶ月間の平均的な水質の様子を診断できる点にあります。川の水を汲んで水質を判定する場合には、その日の状態しかわかりません。前日や夜中に、汚れた水が流れていても分りません。しかし、川の中にずっと住んでいる水生昆虫を調べることで川の状態を総合的に判断することができます。 ■川の水温調査 夏の暑い日に、川の上流から下流にかけて同時に水温を測定します。川の水温は、実は水質以上に大切な要因です。冷たい水を好む生物にとって、川の水が30℃をこえるようならば、サウナに入っているようなもので、すぐにいなくなってしまいます。この調査の場合、どこで川の水温が高くなるかが一目両全で、対策を考えやすいのが利点です。 ⇒千種川での水温調査の結果 |

Copy Right 2005, Museum of Nature and Human Activities,Hyogo
Revised