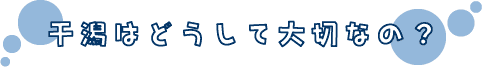|
左の写真は、兵庫県加古川の下流にできた干潟です。 河口になると流れが緩やかになる上に、海から波や潮の満ち引きの影響で、上流から運ばれてきた土砂や有機物(葉っぱのクズや土など)が溜まり、泥だらけの浅い場所ができます。これが干潟で、泥の上にはヨシなどの植物が生えて、様々な生物のすみかになっています。 上流から運ばれてくる落ち葉くずなどの有機物、海から運ばれてくる海藻などのきれっぱし、泥の上で大増殖する微細な藻類は、どれも水生生物の貴重な餌になっています。落葉クズや藻類をカニや貝類、ゴカイなどが食べて、それを魚や鳥が食べることになります。 ここで重要なのは、 さまざまな栄養源が海や上流から流されてくることです。干潟にはいろいろなものが集まってくるのです。上流から絶えず栄養豊かな水(窒素やリン)が流れてくることがとても重要なのです。 もうひとつ覚えておかないといけないことがあります。それは、干潟はどこにでも出来るわけではないことです。川の下流や、湾になっていて波が穏やかな場所にしか、干潟できません。特に、大きな川で自然な状態が保たれている川の河口には干潟ができやすいのですが、埋め立てや開発によって、全国各地の干潟が消失しつつあります。貴重な生態系である干潟はかけがえのない自然環境なのです。 |
|
|
|

Copy Right 2005, Museum of Nature and Human Activities,Hyogo
Revised