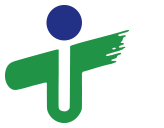インドネシアは広い国です。広い国土と自然の中で人びとがさまざまにくふうしたために、文化や食べ物もさまざまです。もともとインドネシアはひとつの民族からなり立っているというよりも、さまざまな民族がより集まってできた<人工の国>でした。ですから、もともとは民族集団ごとに特色のある文化があり、料理があったのです――料理はりっぱな食の文化です。ところが、そのようなインドネシアにも、例外的にひろく拡がった料理があります。それはパダン料理です。
パダン料理は「インドネシア料理」と紹介されることがありますが、もともとスマトラ島の一地方料理、ミナン・カバウの料理でした。ミナン・カバウは西スマトラ州のミナン・ハイランドと呼ばれる山岳地域を中心に住んでいたのですが、今では西スマトラ州――そこにパダンという都市があります――はおろか、インドネシア全体にひろがりました。なぜ、そんなに広がったのでしょう?それはミナン・カバウの伝統社会のあり方と、おおいに関係があります。

(写真:パダン料理店 屋根は典型的な「ウシのつの」型をしています。建物の右下には、外からでも見えるように、いくつもの料理が並んでいます。)
皆さんは母系(ぼけい)社会という言葉(ことば)をご存じでしょうか?現在の日本では、人は死ぬ前に遺言(ゆいごん)を書いておけば、たとえば自分の財産(ざいさん)を受け取る人を決めておくことができます。遺言がなかったら、男であるか女であるかを問わず、家族ならどの人でも、法律で決まったわりあいで受け取ることができます。財産以外では、これは法律で決めてあるわけではありませんが、たとえば誰がお墓を護(まも)るのかといったことを習慣として決めておきました。このことを相続(そうぞく)と言います。母系社会というのは、その相続が母や母の祖先から娘にされる社会です。前回、紹介したアグロフォレスト(=屋敷林:やしき・りん)も、ミナン・カバウの人たちにとっては母の持ち物であり、娘に引き継がれるべき財産です。
ミナン・カバウは、現在でも母系社会をたもっています。ただ母系社会とはいっても、お父さんの役目は、日本で見るのと変わりはありません。ある日、パダンのアンダラス大学でお世話になった先生のおうちで、夕食をごちそうになったのですが、その家庭のホスト役は、おだやかなお父さんが、もの静かに務めておられました。母家長(ぼ・かちょう)であるはずのお母さんはごちそうをつくるのに忙しく、あまり長い間おしゃべりをしたという記憶はありません。
いずれにせよ、システムとしては母系の社会なのです。そして旅が自由にできる社会でもあるのでしょう。土地にしばられるようなかつての日本では考えにくかったことですが、男たちは皆、商人としてあちこちに散っていきます。そんな商人のうち、料理の好きな男たちが、自分たちの食べている料理を食堂に並べたのです。それは出身地の名前をとって「パダンの料理」、つまりパダン料理と呼ばれました。これが「インドネシア料理」の代名詞であるパダン料理の由来です。
パダン料理店では、お客が食事に来ると、まず、小皿に盛った肉やさかなを、これでもか、これでもかと、お客の前のテーブルいっぱいに並べます。その中から、お客は、自分の食べたいものを好きなだけ食べ、最後に店員が客の食べたものを確かめて、お金を請求するというやり方です。この方法だと、自分の腹具合にあわせて好きな物をほしいだけ食べらます。その上、あまりインドネシア語ができなくても問題にはなりません。よい制度だと思うのですが、でも、ついつい食べ過ぎてしまう人もいるかもしれません。
 (写真2:レストランで働く若い男たち 女に比べて圧倒的に多くの男、というより少年が働いています。)
(写真2:レストランで働く若い男たち 女に比べて圧倒的に多くの男、というより少年が働いています。)

(写真3:わたしの前に並んだ料理の数かず すべて食べるわけではありません。基本的に、牛肉と鶏肉、それに魚料理です。左の白いひげ面がわたし。右はアンダラス大学の講師リザルディさん。)
スマトラ島はインドネシアでは、いちばんイスラームの影響が強いところですから、パダン料理ではブタ肉とお酒は絶対に出ません。豚肉とお酒は、イスラームではタブーです。それにインドに近いからでしょうか、パダン料理にはカレー粉をよく使います。「インドネシア料理」とカレー粉の取り合わせは、パダン料理の影響だと思います。でもパダン料理には、ほとんど野菜を使いません。ミナン・カバウの人たちは、野菜の代わりに果物を大量に食べて、繊維質やビタミンを補うのだそうです。それでも、西スマトラは高血圧の人が多いのだと聞きました。
 (写真4:屋台に並べられたドリアン パダンの街(まち)はドリアンの季節でした。家のアグロフォレストから取ってきて、屋台に並べます。すると、ほしい人がひとつひとつ品定めをして、よいと思うドリアンを割ってもらいます。すると大きな種を包む甘い種皮があらわれます。ほおばるとカスタード・クリームのようです。)
(写真4:屋台に並べられたドリアン パダンの街(まち)はドリアンの季節でした。家のアグロフォレストから取ってきて、屋台に並べます。すると、ほしい人がひとつひとつ品定めをして、よいと思うドリアンを割ってもらいます。すると大きな種を包む甘い種皮があらわれます。ほおばるとカスタード・クリームのようです。)
あちこちに散っていったミナン・カバウの人たちは、パダン料理を食べるとき以外でも、郷里である西スマトラの山や田んぼをなつかしく思うのでしょうか?
なつかしく思うのだと思います。たとえば、インドネシアで一番大きな大都市ジャカルタには、ミナン・カバウの各村の同郷会があります。この同郷会は、たいへん人びとの結びつきが強く、たとえジャカルタ生まれであったとしても、自分はミナン・カバウだという思いは消えないそうです。
その他にも、在ジャカルタ・西スマトラ州連絡事務所という、まるで「ミナン・カバウ大使館」のようなはたらきをしている事務所や、ミナン・カバウの伝統的な踊りや音楽を演ずるための組織、ミナン・カバウの言葉を守ろうというのでしょうか、ミナン・カバウ・アナウンサー協会といった専門家の団体まであります。このようなミナン・カバウの組織は、今でも、西スマトラの郷里に残る人びとと深い精神的つながりを絶やすことはないようです。
わたしは昔から、パダンや西スマトラ州周辺のべつの都市を訪れたとき、若い男性のなれなれしさにおどろいたことがありました。そのような「なれなれしさ」は、この文章を書いていて、旅と漂泊(ひょうはく)の裏返しなのではないかと気がつきました。父系(ふけい)社会と土地にしばられた日本では、なかなか見られなかったことです。でも漂泊の人生は、たとえば中国やインドの人びと、「アラブの商人」と呼ばれるイスラーム世界の人びと、ロマの人びとなど、地球の上では広く見られます。そのことを思うと、案外、日本のような「同じ場所に住み続ける人」の方が珍しいのかもしれないなどと考えたりもします。
今回の文章では、東南アジア研究21巻に載っていた加藤 剛さん(1983)の「都市と移住民:ジャカルタ在住ミナンカバウの事例」という論文を参考にしました。(つづく)
三谷 雅純(みたに まさずみ)
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所/ 兵庫県立人と自然の博物館
※このブログで掲載されている文章・写真の無断転用・転載はご遠慮ください。