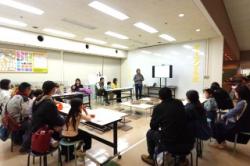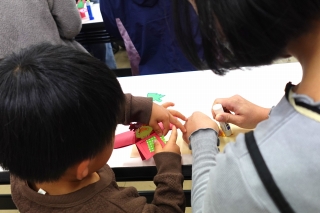ひとはくの周辺(深田公園)には、
色々な植物が植えられていたり、
生えています。
ひとはく本館の横にある長い外階段
沿いにカキノキ(カキノキ科)が
あります。葉っぱは、すでに
落ちています。
※画像をクリックすると、
写真が拡大するものがあります。

▲本館横の長い外階段のそばにある
カキノキ (2025年12月23日撮影)
そのカキノキの枝先には、
小ぶりの果実(長さ約3.5㎝、
幅約3.5cm)が たくさんあります。
どちらかというと、枝先の
果実が残った感じです。
部分的に見ると、3~4ケの
果実が枝先に目白押しです。

▲枝先に残るカキノキの果実
(2025年12月23日撮影)
そこに小鳥が来ました。
逆光気味でシルエット写真に
なっていますが・・・、

▲カキノキの枝に止まる小鳥
(2025年12月23日撮影)
観察していると、すぐに
カキノキの果実(目白押し
でない方)をつつき
はじめました。

▲カキノキの果実を
つついている小鳥
(2025年12月23日撮影)
目白押し でない方の
果実をつついている小鳥
(コトリ)さんは、
目のまわりが白いメジロさん
でした(なんだか白々しい)。


▲果実の一部をくわえている
メジロ(メジロ科)
(2025年12月23日撮影)
いくつかの果実には、メジロ 以外の
鳥類?が食べたのではないかと
思われるものが見られます。

▲鳥類に食べられた跡がある果実
(2025年12月23日撮影)
それは、カキノキの樹冠(じゅかん;
枝のひろがり)下(階段上)に
新鮮な果実の一部が落ちている
からです。


▲階段上に落ちている新鮮な
果実の一部 (2025年12月23日撮影)
これらについては、
よかったら、関連する下記の
ブログ記事をご覧ください。
<関連ブログ記事>
柿食えば、ヒーヨと鳴くなり、果実なくなり?
https://www.hitohaku.jp/blog/2025/12/post_3389/
皆さんも 周辺の環境で生きものの
観察をしてみませんか。
研究員 小舘
色々な植物が植えられていたり、
生えています。
ひとはく本館の横にある長い外階段
沿いにカキノキ(カキノキ科)が
あります。葉っぱは、すでに
落ちています。
※画像をクリックすると、
写真が拡大するものがあります。

▲本館横の長い外階段のそばにある
カキノキ (2025年12月23日撮影)
そのカキノキの枝先には、
小ぶりの果実(長さ約3.5㎝、
幅約3.5cm)が たくさんあります。
どちらかというと、枝先の
果実が残った感じです。
部分的に見ると、3~4ケの
果実が枝先に目白押しです。

▲枝先に残るカキノキの果実
(2025年12月23日撮影)
そこに小鳥が来ました。
逆光気味でシルエット写真に
なっていますが・・・、

▲カキノキの枝に止まる小鳥
(2025年12月23日撮影)
観察していると、すぐに
カキノキの果実(目白押し
でない方)をつつき
はじめました。

▲カキノキの果実を
つついている小鳥
(2025年12月23日撮影)
目白押し でない方の
果実をつついている小鳥
(コトリ)さんは、
目のまわりが白いメジロさん
でした(なんだか白々しい)。


▲果実の一部をくわえている
メジロ(メジロ科)
(2025年12月23日撮影)
いくつかの果実には、メジロ 以外の
鳥類?が食べたのではないかと
思われるものが見られます。

▲鳥類に食べられた跡がある果実
(2025年12月23日撮影)
それは、カキノキの樹冠(じゅかん;
枝のひろがり)下(階段上)に
新鮮な果実の一部が落ちている
からです。


▲階段上に落ちている新鮮な
果実の一部 (2025年12月23日撮影)
これらについては、
よかったら、関連する下記の
ブログ記事をご覧ください。
<関連ブログ記事>
柿食えば、ヒーヨと鳴くなり、果実なくなり?
https://www.hitohaku.jp/blog/2025/12/post_3389/
皆さんも 周辺の環境で生きものの
観察をしてみませんか。
研究員 小舘