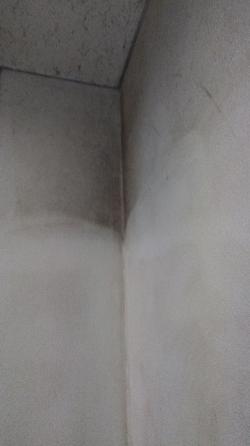地層からプレパラートを作り、ケイソウ化石を顕微鏡で観察します。第1回において採取してきた試料を使い、第2回と第3回は、博物館内でプレパラート作製、顕微鏡観察を行いました。今日はその3回目、プレパラート作製、顕微鏡観察とまとめを行いました。

まずは、顕微鏡の使い方の復習です。
前回作製したプレパラートを装着して、顕微鏡をのぞきます。ピントを合わせるのも上手にできるようになっています。
そして、今日はいよいよ、100万年以上前の地層の試料から4つのプレパラートを作ります。試料に水を加えてかき混ぜ、上澄み液を取り出します。そして一部をスポイドに取ってカバーガラスにのせて乾かし、専用の接着剤でスライドグラスに接着します。ラベルを張ってどの地層から作ったプレパラートかわかるようにします。
完成したプレパラートを顕微鏡で見てみます。資料を見ながら、見つかるケイソウ化石の種類や生きていた場所(湖や海など)を調べていきます。
午後からは、さらに詳しく調べ、たくさんのケイソウ化石を観察することができました。
そして、試料ごとのケイソウ化石の違いから、調査した地域が110万年ほど前に湖や川から海に変わったことや、当時海底であったこの地域がその後100m以上も隆起したことが分かりました。
◎参加された小学生の感想など
・ケイソウやプランクトンなどの小さな世界に興味があって参加しました。
・父親が調べて申し込んでくれました。楽しかったです。
・ピントが合うとはっきりケイソウが見えました。姉妹で参加しました。
◎廣瀬主任研究員より
・子どもたちは大学生が行うような、とても高度な作業に挑戦しました。
顕微鏡で見つけたケイソウ化石の同定も大変的確で驚きました。
ケイソウ化石から100万年以上前の瀬戸内海の様子を探ることができました。
(文責 生涯学習課 ※この記事に関するお問い合わせは、生涯学習課までお願いします。)