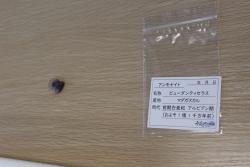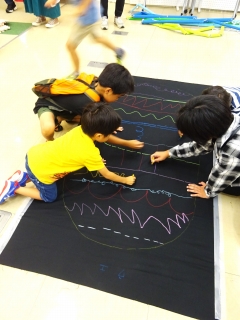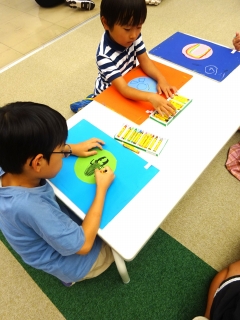道路脇の植え込みや芝生など、普段見過ごしている何気ないところにも昆虫がいます。
「なんでこんなところに虫が?」といった "ナンデナン?" について一緒に考えてみましょう。
まずは、エントランス前の芝生の広場で虫をさがします。
今回は網を使わずに、素手でつかまえ、袋に入れます。山田主任研究員の「はじめましょう」の言葉もそこそこに、子どもたち(おとなたち)が走り出しました。
あちこちで「捕まえた!」と声が上がります。
捕まえた虫について、研究員に名前を確認しています。採れた虫の説明も聞きました。
 |
 |
キッズサンデーのそとはくでも虫とりが行われていました。朝からたくさんの虫をつかまえたようです。
名前のわかるシートも準備してあったので、自分の採った虫の名前を確認してみましょう。
今度は恐竜ラボの裏手へ行って、木や植え込みのある場所で、虫をさがしてみましょう。
おっと、ここは思った以上に蚊が多くて、たいへんたいへん。
猛暑であまり見なかった蚊が、今になってたくさん出てきたようです。
ちょっと早めにこの場所から退散です。
さて、場所が違うと取れる虫も違う、今日のナンデナンの答えはもうわかりましたか?
エサがある、隠れて身を守ることができる、仲間がいるなど、その場所に住むのには理由がありました。だから採れる虫も違うんだね。参加してくれたみんなはわかってたよね。
◎参加したみなさまの感想など
・カメムシやゴキブリも、そして蚊も捕れました。
・網がなくても手で捕まえられたよ。
・もっと捕まえたい!
観察する場所を変えたら見つかる虫も違いましたね。なぜ場所が変われば見つかる虫が変わるのでしょうか?答えはいろいろありますが、理由がわからないこともあります。普段から身近な場所に目を配って、いろいろな虫を探して、その理由について思い巡らせてみてください。虫の見方が変わるかもしれませんよ。
(文責 生涯学習課 ※この記事に関するお問い合わせは、生涯学習課までお願いします。)