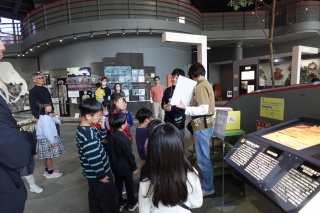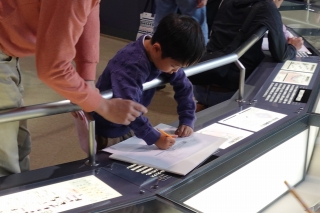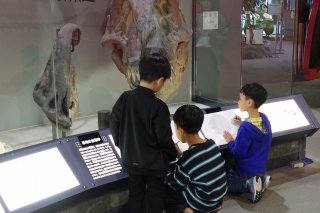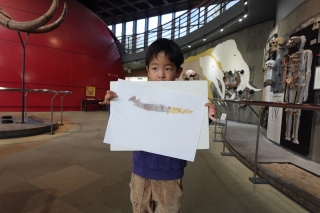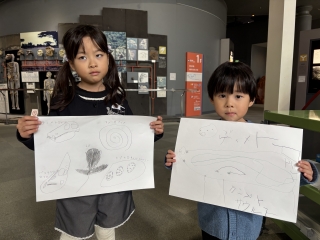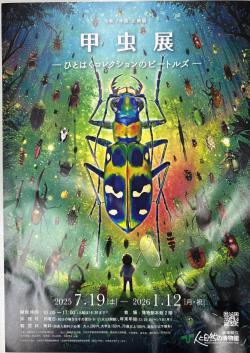ひとはくKidsサンデーです。
11月に入って、ひとはくに隣接する
深田公園では、緑道沿いのケヤキ
(ニレ科)の葉が黄色や赤色
になって落葉しはじめています。


▲深田公園の緑道沿いのケヤキと
その落ち葉
11月の Kidsサンデーの
主なプログラム の ようす の報告で~す。
<エントランスホール前の芝生地では・・・>
■「そとはく」のようすは・・・
今回の「そとはく」では、
『どんぐりコロコロ』
が実施されましたよ。
クヌギ(ブナ科)の果実(ドングリ)や
トチノキ(トチノキ科)の果実・種子など
を専用の長いレーン上で転がすプログラム
です。


▲専用のレーン上で ドングリなどを
転がしているようす
小さな子どもさんたちは ドングリなど
をレーンで転がして、それを追いかける
ように一緒に走って楽しそうでしたよ。
<コレクショナリウムでは・・・>
■「風に乗って飛ぶタネの模型を
つくろう」のようすは・・・
研究員の話を聞いて・・・。
さあ、模型をつくってみましょう。


▲お話を聞いて模型をつくっているところ
フタバガキ(フタバガキ科)や
ニワウルシ(ニガキ科)の
タネ(果実)の模型を紙やホッチキス、
クリップなどを使ってつくって
飛ばしたようですよ。
皆さん、上手く飛びましたか?
<本館内では・・・>
■「エコロコおやこ『葉っぱぐるぐるを
つくってあそぼう!』」
の ようすは・・・
親子で、ドングリ(堅果)が
できる木の葉っぱ(3種類)から
自分の好きな葉っぱを選んで
葉っぱの おもちゃ「葉っぱ
ぐるぐる」をつくります。

▲「葉っぱぐるぐる」を
つくっているところ
つくった おもちゃ で早速
あそびます!





▲葉っぱの おもちゃ で
遊んでいるところ
うまくできましたネ~
■「超本格!化石クリーニング
体験セミナー」のようすは・・・
専門的な道具を使って化石の
クリーニングの体験をした
ようですよ。

▲研究員の話を聞いているようす
標本(化石のレプリカ)を
クリーニングしているところ
の写真を撮らせてもらいました。

▲実態顕微鏡下で、専用の道具を
使ってクリーニングしているようす
また、クリーニングした後の標本
を見ているところも
写真に撮らせてもらいました。

▲実体顕微鏡で観察しているようす
参加された皆さん、
本格的なクリーニング体験、
いかがでしたか?
■ひとはく連携活動グループ
人と自然の会 の皆さんによる
「おはなしシアター」のようすは・・・
今回は、「さるかにがっせん」と
「さんまいのおふだ」が上演された
よそうですよ。
上演前の練習風景を写真撮影
させてもらいました(集中して
練習されているため、撮影して
いることをすぐには気が付いて
くれませんでした)。

▲上演前に練習をされているところ
会場でご覧になった皆さん
どうでしたか?
■フロアスタッフと研究員による
「ひとはく探検隊『秋の昆虫かんさつ』」
のようすは・・・

▲『秋の昆虫かんさつ』の看板
受付開始後すぐに、定員に
達したようです。
下記のブログがありますので、
こちらを ご覧ください。
こんにちは!フロアスタッフです♪
~ひとはく探検隊「秋の昆虫かんさつ」~
https://www.hitohaku.jp/blog/2025/11/post_3359/
フロアスタッフによる
『デジタル紙芝居』や『展示解説』
も 実施されましたよ。
次回のKidsサンデーは、2025年12月7日(日)です。

ご家族で、ひとはくへ お越しください。
Kidsサンデープロジェクト 小舘