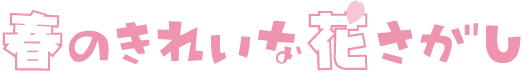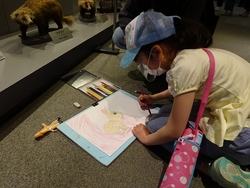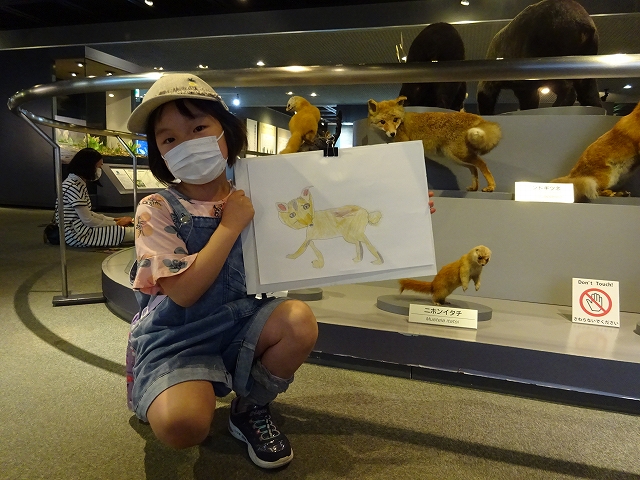ひとはくの周辺のソメイヨシノは、花が終わり、
葉が展開し始めました。


▲ひとはく周辺のソメイヨシノのようす(花びらが散ってしまった)
ひとはくに隣接する野外施設の円形劇場のそばに樹林があり、
そこにはソメイヨシノとは違う野生のサクラ類の木があります。

▲円形劇場のそばの樹林
それは、ウワミズザクラという名前で、1つ1つの花は小さくて
それらが(コップ洗い用のブラシのように)穂状になっています。

▲円形劇場のそばにあるウワミズザクラの木
4月12日にウワミズザクラの花が咲いているのを
確認しました。

▲ウワミズザクラの花序(下の方から花が開いている)
じつは、4月8日の時点で同じ木のつぼみが膨らんでいるのを
観察していたのです。

▲ウワミズザクラの花序(つぼみ)
その日、ウワミズザクラを観察をしようとして木に近づくと、
円形劇場の床部分で、何かが動く気配がしました。
そちらの方をみると、そこには小鳥がいました。
ヤマガラのようです。

▲円形劇場の床部分にいたヤマガラ
ヤマガラも見られているのに気付いたのか、上空の
ウワミズザクラの枝へ飛んで行き、しばらくして、
また下へ降りてくる動作を数回繰り返していました。

▲ウワミズザクラの枝に止まるヤマガラ

▲階段状になっている部分にいるヤマガラ
こちらも、しばらく床部分や階段状の部分にいる
ヤマガラの方を観察していました。
ヤマガラは、床部分に落ちているヤマモモの種子(前年のもの)を
つついていました(つついていたのですが、この時は飲み込んでは
いなかったようです)。
ウワミズザクラは8月くらいに果実が熟します。そのころには
いろんな小鳥たちが食べに来るのでしょうね。
研究員 小舘 誓治