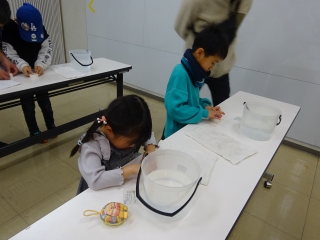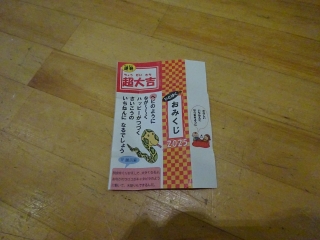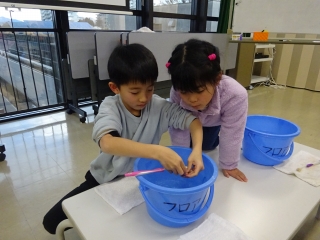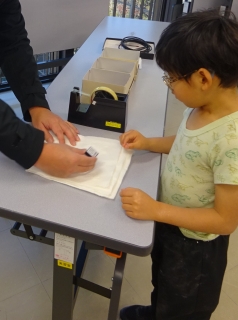トウネズミモチ(モクセイ科)の
高木(高さ約10m)があります。
1月中旬~下旬、その木には、
1週間くらいで集中的に
ヒヨドリ(ヒヨドリ科)が
果実を食べに来ていました。
この木の枝葉の広がりの下には、
コンクリート製の外階段や、
樹林の地表面および他の植物が
生えていたりします。
ヒヨドリが来るようになって
階段の表面や手すりの部分に
鳥類のフン?と思われるものが
たくさん落ちているのが
見られます。
画像をクリックすると、写真が
拡大するものがあります。

▲階段のコンクリート面に落ちている、
トウネズミモチの 果実や種子、
葉、枝、鳥類のフン?など

▲階段の手すり部分に落ちている
鳥類のフン?など

▲カンツバキの葉に落ちている
鳥類のフン?など

▲トウネズミモチの高木の下の方の
枝の葉に落ちている鳥類のフン?など
それらの鳥類のフン?と思われる
ところにトウネズミモチの種子
があったりします。
ちなみに1月下旬に採集した
トウネズミモチの種子の写真を
撮ってみました。
果実は熟していると思ったのですが、
その中の種子は緑色でした
(まだ十分熟してない?)。

▲トウネズミモチの種子
(縦方向にシワがあります。
熟すと茶色っぽくなる?)
トウネズミモチとしては、遠くへ
行ってフンをして(種子散布をして)
ほしいと思っていることでしょう。
トウネズミモチの高木の近くに
ヒラドツツジ(ツツジ科)の
植え込みがあります。
この植え込みは、定期的に高さを
1mくらいに伐り揃える手入れが
されています。
しかし、その揃えられた高さよりも
高く成長したトウネズミモチが
複数見られたりします。


▲ヒラドツツジの植え込みから
伸びたトウネズミモチ(1月下旬撮影)
それらは、手入れのときに
ヒラドツツジと同じ高さに
伐られるのですが、
伐られた位置の近くから
新しく枝を伸ばして再生し
高くなっています。

▲伐られた跡があるトウネズミモチ
毎年、種子が供給されているようで
ヒラドツツジの植え込みの中に
トウネズミモチの幼木や双葉などの
実生個体(種子から発芽して生じた
もの)が見られます。

▲ヒラドツツジの植え込みの中の
トウネズミモチの実生個体
(1月下旬撮影)
種子が散布された(食堂でいえば、
暖簾(のれん)分け?をしてもらった)
のですが、まだ、果実や種子を作るまで
には至っていない(食堂としてオープン
できていない?)という状況でしょうか。
皆さんも 周辺の環境で生きもの
の観察をしてみませんか。
研究員 小舘