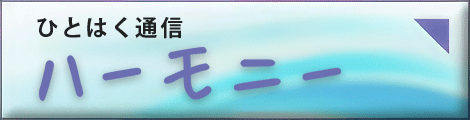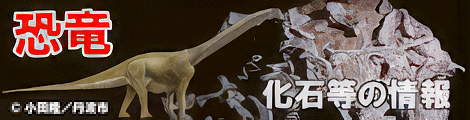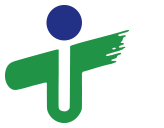ユニバーサル・ミュージアムをめざして56
人の多様性をマネジメントする?
三谷 雅純(みたに まさずみ)
「私の眼前に一頭のインパラが現れた。黄金の草地に足を着き、透き通る大気に首を立て、たった一頭でたたずんでいた。インパラは草を食むこともなく、歩きまわることもなく、緊張している様子でもなく、だからと言って気を抜いてくつろいでいるふうでもなかった。誰かに追われることもなく、誰かを追いかけることもなく、静かにそこに立っていた。インパラの濡れた美しい目は、周囲のすべてを吸収し、同時に遠い世界を見据え、遥か彼方を見渡していた。」(中村安希『インパラの朝 ユーラシア・アフリカ大陸684日』集英社文庫)
アメリカ合衆国の大手優良企業の間では、1990年頃から「ダイバーシティ・マネジメント」(=人の多様性マネジメント:さまざまな人が力を合わせて企業のために努力すること)講習が大流行だという噂を聞きました。わたしは「ダイバーシティ・マネジメント」という言葉を知らなかったのですが、調べてみると、個別の多様な意識を持った人から成るアメリカでは、従業員を雇う時には、従業員の意識を大切にしなければ企業としての連帯感は芽ばえない。例えて言えば、中国出身の漢族のお母さんとスペイン出身のラテン系のお父さんがいる女性がいたとして、その女性を雇いたいなら、それぞれの民族性とその女性が混血であるという事実を大切にした職場環境を作らなければならないという事です (1) 。
今は「ダイバーシティ」、つまり「人の多様性」を問題にするのですから、性別やジェンダー、青年とか高齢者とかといった心の発達段階、さまざまな障がい、それに(生物学的には実在しないが)社会的な「人種」、つまりアフリカ系かアジア系かといった特徴も大きな問題になります。このようなもろもろの差異をていねいにフォローしていかなければ企業としての生産性は上がらない。第一、評判が悪くなる。反対に、社員が持つ多様性を有効に生かせれば、ものを買う消費者の本心まで引き出せる。これは「高齢の女性は髪の毛がペタンとしてしまうのを気にしている」とか、「若い男性は仕事が忙しくて海に行けず、そのせいで肌が焼けないのを気にしている」といった類のことです。こういったことは、当人でなければ、なかなか気が付きません。しかし従業員にとって他人事でないのなら、企業も従業員を通してそれに気づき、商品開発に生かせる。こうすれば多様性は生かせる。そういう理屈です。
そう言えば、アメリカの子ども向け番組「セサミ・ストリート」は、子どもが、「社会にはいろいろな人がいる」と素直に認識できるように作られていると聞いたことがあります。確かにエルモやクッキー・モンスターは、わたしの知るあの人やこの人を思い出させます。おまけにビッグ・バードというキャラクターにいたっては、人でなく鳥だということです。
ただし「ダイバーシティ・マネジメント」は、現実のアメリカにあるビジネス潮流です。ユニバーサル・ミュージアムのような(日本では、まだまだ?)「夢物語」や「絵空事」ではありません。企業に「ダイバーシティ・マネジメント」を教えるコンサルタントには、一日当たり平均 2,000 ドル、日本円では20万円以上ものお金が支払われるそうです。有名なコンサルタントだともっと高いそうですし、中には長期契約で数百万ドル(数億円!)ものお金を支払わないと引き受けないというコンサルタントまでいるそうです (2)。
☆ ☆
それにしても、アメリカの「ダイバーシティ・マネジメント」、つまり「人の多様性」のマネジメントですが、先ほども書いたように、わたしはその存在を知りませんでした。自然科学や博物館運営の話ではなく、基本的にビジネスの世界の出来事です。「ダイバーシティ・マネジメント」には限りませんが、世事に疎いわたしには、知らないことは多いのです。それでも「人の多様性」なのですから、このコラムを連載する者としては、うわさぐらいは聞いていてもよさそうです。それが聞いたこともなかったのです。
欧米発の情報なら、「グローバル経済」や「市場主義」、あるいは「競争社会」でさえ、日本社会は喜んで取り入れてきました。ところが「ダイバーシティ・マネジメント」がわたしの耳に届くことはありませんでした。不思議な思いです。これはいったい、どうしたことでしょう?
「競争社会」や「市場主義」は、そう呼ばなかっただけで、最初から日本社会には根付いていたものだと思います。例えば「丁稚(でっち)」という制度は少年たちを下層労働で競わせましたし、商人の商いは「ものを売る」ことが基本です。このような習慣は自然に企業に引き継がれ、現代風に名前を変えたのです。「グローバル経済」は少し説明が必要ですが、要は商家の需給バランスが崩れ、規模が大きくなって、国境を越えなければ身の置き所がなくなっただけ。そんな気がします。少なくとも企業倫理や経営志向(嗜好?)は何も変わっていない。もとのままで日本の企業は国際企業になった。違うでしょうか?
それならば「ダイバーシティ・マネジメント」は、なぜ取り入れられなかったのでしょう? 「『日本人』は同質性の高い民族グループだからだ」という意見が、今、確かに聞こえました。確かに同質性は高いのです。なぜなら、今では習い性のようになった水稲耕作(すいとう・こうさく)の労働習慣では、陸稲(おかぼ)や雑穀(ざっこく)の栽培よりはるかに、人びとが力を合わせた労働力が求められるからです。収穫量の多い水稲を基本にする限り、日本に住む人びとは、例え民族グループが異なっても、同じ顔をして労働しなければならない。それができなければ村八分になるか、アジール (3) にでも行くしかありません。
「ダイバーシティ・マネジメント」は「日本人の舌には合わなかった」。だから最初からなかった事にしてしまった。それが真相ではないのでしょうか。
これは、言ってみれば「しろうと談義」です。しかし、まったく根拠のないものでもありません。昔から親しくしているある学校友だちと気楽な話をしていて――わたしの友人の中では数少ない企業人です――彼の言ったことを思い出し、なぜなのだろうと考えた結果です。
☆ ☆
中村安希さんはバックパックで世界を回るノンフィクション作家です。アメリカのカリフォルニア大学アーバイン校で舞台芸術学を修められ、日本に帰って「母国の社会へ適応するため、できる努力はしていた」時に、イラクに行った日本人青年が人質になり、命を落とすという事件が起こりました。次の文章は、中村さんがお書きになった『インパラの朝』 (4) という本に載っていたものです。ヨルダンの安宿で聞いた爆撃音の振動を描いた「ヨルダン [夜空に散る火花]」という章にありました。
「私はテレビの前に座って、遠いどこかの国で人が死ぬのをじっと見ていた。そして私はいつの間にか、迷惑を被った人になった――血税を納める納税者として、日本国民の一員として。随分とのん気な迷惑だった。
多角度的な論争や事情の細かい検証は、日増しに敬遠されていったし、代わって論調の統一と事態の安易なフレーズ化が、好意的に受け入れられた。事件の神髄や世界の裏面の抜本的な再考なんて、聞いただけでも面倒だった。政府もメディアも国民も、事件に早く決着をつけ、さっさと忘れてしまいたかった。青年はイラクで見捨てられた。イラクで人がたくさん死んだ。誰かが大声でこう言った。
『反日分子』
分子? 私は化学が苦手だった。」
中村さんは日本での一見平穏な仕事に苛立ちを深め、「経済的な優位性と人的犠牲が組みになり、人命の尊重と経済面の不利益が別の組みになっていて、世界に可能な選択はその二組に一つのはずだったが、現実は四つを混同させて、建て前と本音に再分割した」のだと考えたそうです。そしてこの章を、次のように締めくくられます。
「不運にも事件に巻き込まれたら......。恐ろしいことが待っているだろう。恐ろしいのは人質になることや犯人からの暴行ではなく、日本の世間の冷笑や、残してきた日本の家族への激しい批判と非難だった。両親は国家に頭を下げて世間に許しを乞うてでも、娘の命を救うために命乞いをするだろうし、それを止める権利はない――国家に個人を救えるだけの力があるかは別として。
けれど、と、私は考えている。それが子から親に対する残酷な要求と知りながら、それでも無理を望むなら、運の尽きた娘について胸を張って語ってほしい。誰かに聞かせる必要はない。ただ呟(つぶや)くだけで構わない。
『とても幸せな娘でした。少なくとも自宅のテレビの前でポテトチップスを食べながらぼんやりと座っていたのではなく、現実と彼女の間の距離をたとえわずかであったとしても縮めようとする試みの中で志半ばで敗れたのだから。あの子は日本が好きでした。だから日本を離れました。そして、世界が好きでした』と。」
もちろん微妙に違いますが、世界や日本に対しては、わたしも似た感情を抱いています。
---------------------------------------------
(1) 谷口真美さんという早稲田大学の先生がお書きになった論考が役に立ちました。
谷口真美 (2008) 組織におけるダイバシティ・マネジメント. 日本労働研究雑誌 574/ May: 69-84.
http://eforum.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2008/05/pdf/069-084.pdf
(2) ダイバーシティ・マネジメントのコンサルタント料については、
有村貞則 (2000) ダイバーシティ・トレーニングの失敗とその原因. 山口経済学雑誌 47: 69-118
file:///C:/Users/mitani/Downloads/C050048000403%20(2).pdf
の73ページに載っていました。
(3) 歴史家の網野善彦さんのお書きになった『無縁・公界・楽――日本中世の自由と平和』によれば、アジールとは地域コミュニティーを逸脱した人が、どうどうと暮らせる場所であったそうです。犯罪者や離婚をしたい女性などもいましたが、盲人やハンセン病者もアジールに逃げ込んだということです。そういえば、宮崎 駿さんの映画「もののけ姫」の中で、砂鉄から鉄を採るタタラ場には、顔を包帯で包んだハンセン病者や多くの女性がいたことを思い出します。
『無縁・公界・楽――日本中世の自由と平和』(網野善彦、平凡社ライブラリー150)
(4) 中村安希『インパラの朝 ユーラシア・アフリカ大陸684日』(集英社文庫)。「ヨルダン [夜空に散る火花]」は、この本の115ページから119ページにありました。
http://www.shueisha.co.jp/shuppan4syo/21nen/outline01.html
三谷 雅純(みたに まさずみ)
兵庫県立大学 自然・環境科学研究所
/人と自然の博物館