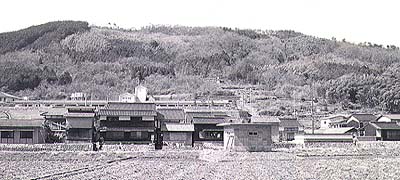
里から山をみる(佐用町)
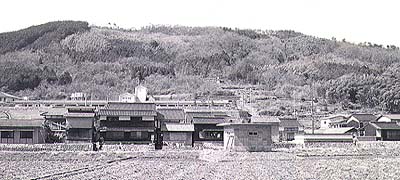
「むかしむかし、あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へ洗濯に...」というのはおなじみの「桃太郎」の冒頭の部分ですが、このお話に出てくるように、人が入り込んで「しばかり」をするような、人の暮らしとむすびついた山を「里山」といいます。
「しばかり」というのは、木の細い枝(柴)を刈り取ることです。柴は火のまわりがよく、火力が調整しやすいので、炊事によく使われました。木の幹を短く切り、縦に割った「割り木」は柴と違って長い時間燃やし続けられ、いろりや、まとまった火力が必要なお風呂に使われました。松の木の根は、石油ランプが普及する前には細かく割って明かりをとるのに使いました。
近くに里山がない人たちはどうしていたのでしょうか。都市が発達すると、里山から遠く離れた場所に持ち運ぶ燃料として、炭を焼きました。柴や割り木は重たくて、大勢の人のために十分な量を運ぶことはできませんが、炭にすれば非常に軽くなります。有名な「紀州備長炭」というのは、ウバメガシから作った炭で、紀伊田辺の炭問屋「備中屋長左ェ門」が、今の和歌山県からはるばる大阪や江戸まで運んだのでこの名があります。備長炭は、うちわなどであおいで火力の調整ができ、柴が手に入らない都市で炊事用に重宝され、現在でもよい炭の代名詞です。博物館の展示でおなじみの兵庫県の猪名川町でクヌギを焼いて作られる一庫炭(池田炭)は、その形が美しく、お茶に用いられる最高級の炭になっています。
里山からとれるのは燃料だけではありません。山の一部は、火入れで草地に保たれ、屋根を葺く茅をとりました。水を引くための樋や、荷物をかつぐかご、棹などなど、様々に用いるために、里に近い部分にモウソウチクが植えられました。紙の原料も里山からとれます。西宮市名塩で作られ、京都や金沢で金屏風などにする和紙「名塩紙」は六甲山のガンピを主原料に、ノリウツギからとった糊を使って漉かれるものです。
田や畑に用いる肥料も里山からとれました。燃料を燃やしたあとの灰はカリウムなど植物の生長にかかせない元素を含む無機肥料でした。落ち葉や刈り取った草、地表面近くの肥えた土などは有機肥料として用いました。
昔は(といってもほんの数十年前まで)里山は人々の暮らしに必要な燃料や道具を作る材料、豊かな収穫にかかせない肥料を産み出す場所だったのです。
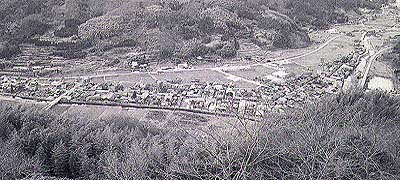
戦後、主なエネルギー源が石炭・石油などの化石燃料になり、炭や割り木、柴などは使われなくなりました。工業が発達し、道具の材料は、金属や合成樹脂などになりました。また、肥料もチリ硝石や空気を原料とする窒素肥料や、鉱物から工業的に作られる無機肥料などにかわりました。人々は山に入らなくなり、里山は様々な物質を産み出す場から、存在意義を失った単なる「裏山」になってしまったのでした。
山から人が去ると、里山はだんだん、その姿を変えてきました。柴や炭をとらなくなった林は、背が高くなり、暗くうっそうとした森に移り変わっていき、春先に私たちの目を楽しませるツツジの花は少なくなり、澱粉をとるために普通に使われていたカタクリはほとんど見られなくなりました。伐採されることも、タケノコをとられることもないモウソウチクはどんどん繁茂して山を覆いつくすかのように広がりだしました。農家にとって貴重な現金収入と肥料を産んでいた山は、なにも産まなくなったので売られ、大規模な造成工事で尾根を切り、谷を埋められ、この博物館のあるフラワータウンのようなベッドタウンやゴルフ場へ姿をかえていきました。
そして、私たちは武者小路実篤が「武蔵野」の中でめでたような美しい雑木林(ぞうきばやし)や、桃太郎のおじいさんが「しばかり」にかよった「里山」の風景に触れるチャンスを失いつつあるのです。
里山は自然に出来たものではなく、自然と人とが働きかけあってできたものです。里山を私たちが心地よいと思う状態に保つためには、私たちが里山に行って、働きかけなくてはいけません。また、里山に生きている生き物たちには、長い間私たち人間の暮らしとともにあったもので、里山が自然にかえってしまうと、いなくなってしまうものが多く含まれています。
そこで、この頃では、里山を里山らしく保つために、木の枝をはらったり、幹を切ったりする活動が始まっています。切り出した木は、炭を作ったり工作の材料にしたりします。手を入れた林では、歩きやすく、野草の花も多く見られるようになります。もちろん里山だったところ全部に手を入れることはできません。しかし、山に入り、木を切りだし、炭を焼くことで、「武蔵野」や「桃太郎」が語るわれわれの文化を次の世代に伝えることができます。
里山の姿は、自然という鏡に、私たちの文化や文明を映したものなのです。私は里山に登り、林に分け入っていくと、つい、我々がどこからきて、どこへむかっているのか考えてしまいます。